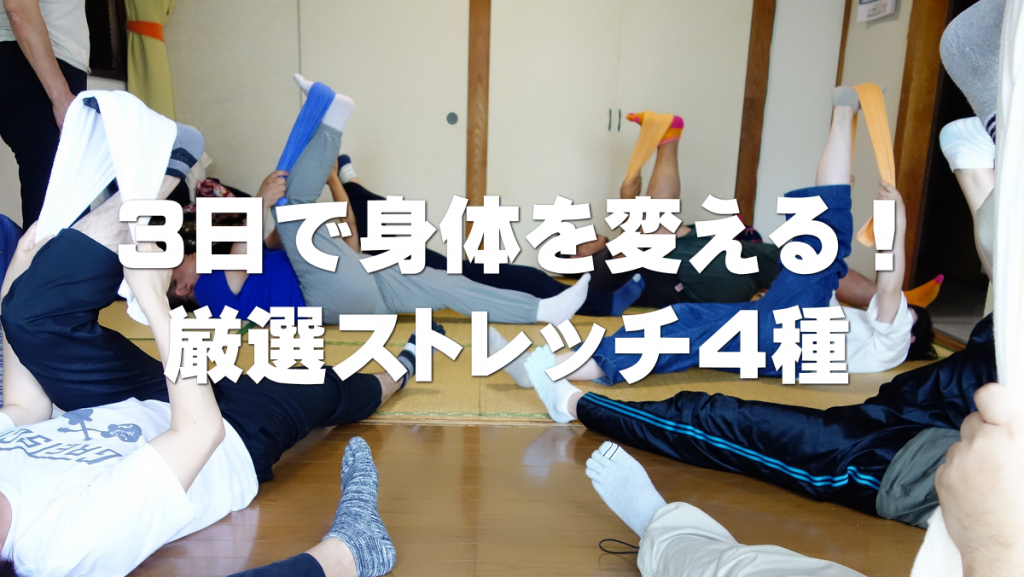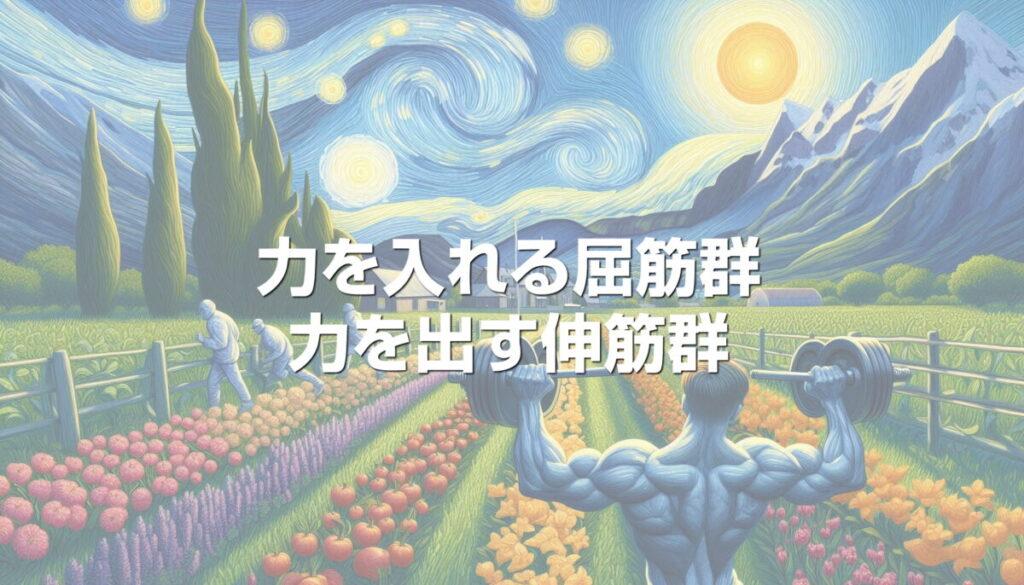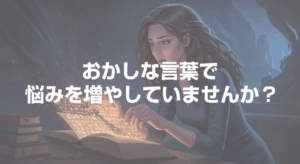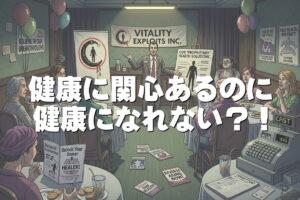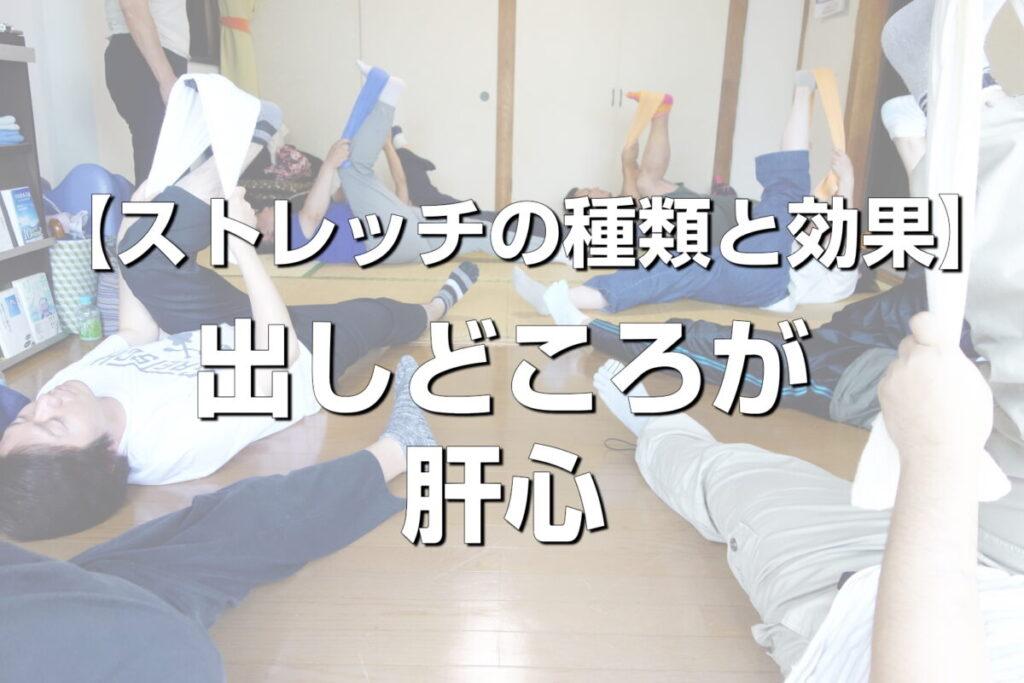

手力整体塾@からだ応援団のパンチ伊藤です。
未だに何故か賛否ありますが、機能解剖を知ればストレッチは必須。どの筋をどのようにストレッチするかがとても重要というお話しです。
出しどころが肝心!ストレッチの種類と効果
ストレッチと一口に言っても広義では様々な種類があり、目的によって適した方法が異なります。主に以下の4つの種類に分けられます。
静的ストレッチ(スタティックストレッチ)

反動をつけずにゆっくりと筋肉を伸ばし、その状態を一定時間キープする方法です。
【目的】
- 筋肉の柔軟性向上・関節可動域の拡大: 筋肉の緊張を和らげ、じっくりと伸ばすことで柔軟性を高めます。
- 疲労回復・リラクゼーション
- 血行を促進し、疲労物質の除去を助けます。 また、深呼吸をしながら行うと副交感神経が優位になります。
- クールダウン
運動で短縮した筋肉を元の状態に戻し、筋肉痛の軽減も期待できます。
【やり方】
- 伸ばしたい筋肉を意識し、ゆっくりと息を吐きながら伸ばします。
- 痛みを感じない、「気持ちいい」と感じる程度で止め、20〜30秒間その姿勢を保ちます。
- 呼吸は止めず、自然な呼吸を続けます。
【適したタイミング】
- 運動後のクールダウン
- 入浴後など体が温まっている時
- 就寝前
動的ストレッチ(ダイナミックストレッチ)

体を大きく動かしながら、筋肉をリズミカルに伸ばしたり縮めたりする方法です。 ラジオ体操やブラジル体操などがこれにあたります。
【目的】
- ウォーミングアップ: 関節の可動域を広げ、筋肉や神経系を刺激することで、運動に向けた準備をします。
- パフォーマンス向上: 体温と筋温を上昇させ、筋肉の弾力性を高めることで、本来の力を発揮しやすくなります。
- 怪我の予防: 筋肉を温めてほぐすことで、運動中の肉離れなどを防ぎます。
【やり方】
実際の運動で行う動きに似た動作を取り入れ、徐々に動きを大きくしていきます。
腕を大きく回したり、脚を前後に振ったりと、関節を大きく動かすことを意識します。
【適したタイミング】
- 運動前のウォーミングアップ
- 起床後
バリスティックストレッチ

反動や弾みを利用して、瞬間的に筋肉を伸ばすストレッチです。
【目的】
- 瞬発的なパフォーマンスの向上
筋肉の伸張反射を利用して、特に競技直前のパフォーマンスを高める目的で用いられることがあります。
【やり方】
リズミカルに反動をつけて筋肉を伸ばします。 例えば、アキレス腱を伸ばす際にリズムをとるような動きです。
【注意点】
反動をつけることで筋肉や腱を傷つけるリスクがあるため、ウォーミングアップやクールダウンには適していません。 十分に体が温まった状態で行う必要があります。
PNFストレッチ

「固有受容性神経筋促通法」とも呼ばれ、神経と筋肉の仕組みを利用したストレッチです。
【目的】
- より高い柔軟性の獲得
他のストレッチよりも高い柔軟性向上が期待できます。 - リハビリテーション
もともとはリハビリのために開発されたテクニックです。 - 筋力強化
筋肉を収縮させる動きも入るため、柔軟性向上と同時に筋力を鍛える効果も期待できます。 - 連動性の回復。
【やり方】
「筋肉を伸ばす→パートナーなどに抵抗を加えて力を入れる→脱力してさらに深く伸ばす」というサイクルを繰り返します。
一人で行うのは難しく、専門知識を持ったパートナーの補助が必要な場合が多いです。
【適したタイミング】
運動の前後どちらでも効果が期待できます。トレーニング前は怪我予防に、トレーニング後は疲労回復に役立ちます。
・・・と、ここまではAIがまとめてくれた一般論。以降ワタクシのターンです。
狭義のストレッチ
大きく分けて、動きを伴わない静的なストレッチと、動きつつ筋ポンプを利用した動的ストレッチ。二種類あることがわかったと思います。
小中学校の体育でイチ・ニ・サーンとか言いながらやっていたのはバリスティックストレッチだしラジオ体操はダイナミックストレッチ。どちらにしても、ストレッチとしてはちょっと特殊なヤツの方が馴染みあるわけです。『狭義のストレッチ』と言えば静的なスタティックストレッチですからね。
『ストレッチ=伸ばす・引っ張る』なので、反動をつけて勢いよく伸ばしても確かにストレッチではあるのですが、ここで、筋肉が持っている無条件反射を思い出すことが大事になります。
- 筋肉は収縮後に弛緩します
筋肉の収縮具合(張力)を感知した腱紡錘(ゴルジ腱器官)により収縮を抑制する反射(弛緩)が生じます。 - 筋肉は引き伸ばされると元へ戻ろうとします
筋肉の伸長を感知した筋紡錘により収縮を起こす反射が生じます(伸張反射)。脚気の検査に用いられる膝蓋腱反射が有名です。
伸張反射を引き合いに出して「ストレッチはするな」という人がたまにいますが、どちらも『反射』なので瞬間的なスピードが肝心。収縮も伸長もゆっくりだったら反射は起きません。
反射を念頭に置き、ストレッチ後にどうなるのかまでを考慮した場合、やっぱり静的なスタティックストレッチこそがストレッチと言えます(プロの手を借りるならPNFも)。ダイナミックやバリスティックは「準備運動」としたほうがシックリきますね。
ストレッチ=柔軟体操?
柔軟体操と言われることもあるストレッチ。確かに、筋肉の柔軟性に一役買いますが、俗に言う体の柔らかさ、関節可動域の広さにはあまり影響を与えません。関節可動域は筋肉の硬さだけで決まるわけじゃないからです。
関節可動域は生まれ持った性質にかなり左右されます。筋肉の柔軟性も白筋多めか赤筋多めか、生まれつきある程度決まっています。
必要以上のストレッチで性質を変えようとするより、持って生まれたものを適切に活かすほうが大事。赤筋多めで持久力が高くちょっと体硬いくらいの方が、現代ではメリットが多いように思います。
特別な演技や競技で必要じゃ無い限り、持って本来の関節可動域回復までを目標に!(スタンダードな関節可動域一覧はこちら)
どの筋肉をストレッチするのか
1番肝心なのはどんな時どの筋肉をストレッチするのかです。
コレを適切に見抜くためには、まず『解剖学的基本肢位』を知る必要があります。

身体中の骨格筋が伸びも縮みもしていない時の姿勢が『解剖学的基本肢位』。全ての関節が元の位置(ゼロ度)にある時とも言えます。
しっかり目に焼き付けてください。筋肉が何もしていなかったら手の平は前を向いてつま先は外を向きます。
脊椎は勝手に生理的弯曲を描き、耳~肩峰~大転子が垂線に重なります。
二足直立ならではの解剖学的基本肢位は物理的にも理にかなっているのです。
基本肢位を知ってか知らずか、個人の状態考慮せず症状別にアレコレとストレッチを提案する人があとを絶ちませんが、基本肢位と比較せずにすすめられるのは↓の4点くらい。
ま、人間の生活環境が似通ってきているのは事実なので、30~40代以降であれば短縮しやすい『屈筋群』のストレッチをしておけばほぼ間違いありません。例外は殿筋群ですね。
間違っても【症状を感じているところ】【基本肢位と比べ伸びているところ】をストレッチしないように。気持ちは良いかもしれないけど次第に悪化しますからね。
兎にも角にも【短縮したまま放置されている筋肉を静的なストレッチで元の長さに近づける】。コレがストレッチの目的ド真ん中。
仰向けで手の平を上へ向けて気持ちよく眠れるようになる為でもあります。逆に言うと、ほぼ基本肢位になる仰向けは1番お手軽なストレッチとも言えます。
ストレッチする際の注意点

- 短縮したまま伸びにくなっている筋肉を
- 運動後や入浴後など筋肉が温まっている時に
- 勢い反動はつけずゆっくりジンワリ
- イタ気持ちいい程度に伸ばして
- 呼吸は止めずに
- ツーンとした感じが抜けるまでキープ(大体60秒。慣れたら30秒ぐらい)
- 楽しいこと思い浮かべながら笑顔で!
んな感じ。
生まれながらに関節可動域がやたらと広い人はストレッチする必要ありません。効きませんからね。
手力整体塾の塾生にも異常に身体が柔らかい人が数名いました。関節可動域がやたらと広いのでストレッチは出来てしまうわけですが、筋肉に触ってみればあちこちにコリがありました。
ヘロヘロなインナーをアウターが補って固くなる。けれどインナーはヘロヘロ故ストレッチは得意。そんな場合は苦手なインナーマッスルをバランス系のスタビライゼーションなどでリハビリしたほうが良いです。あ、動きっぱなしなら別に不都合無いと思うのでそのままで良いんですけどね。
基本肢位から外れた姿勢になっちゃうようならストレッチは必須ですけれど、硬い体でも柔らかい体でも、性質として生まれ持った身体を活かしましょう。
どちらにもメリット・デメリットはあります!
先日の教室が久しぶりにストレッチ講座だったので、ストレッチについてまとめてみました。最後まで読んでいただきありがとうございました!
タネも仕掛けもある【手力】を身につける
自然体が生む Natural Power
タネも仕掛けもある特殊能力を習得